
賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25
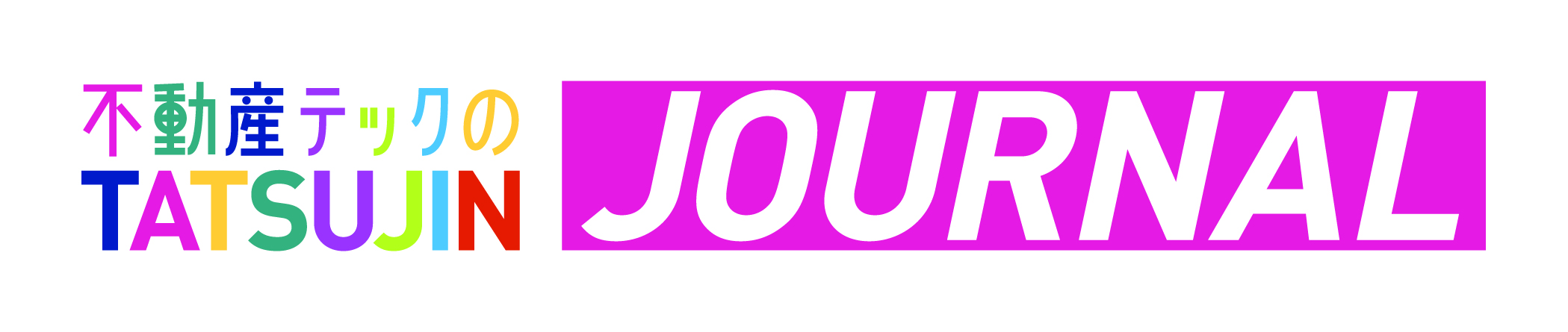

賃貸住宅を退去する際、賃借人は借りていた部屋に対して「原状回復」の義務を負うことになります。
しかし、原状回復にかかる費用を借主である賃借人がどこまで負担すべきなのか、そもそも決まっているのかという多くの疑問がありますね。
原状回復を行う範囲と敷金には、多くのトラブルが発生しています。
2020年4月1日から施行された改正民法では、その原状回復と敷金の解釈が明確化されることになりました。
改正された民法の重要なポイントついて解説していきます。
原状回復とは賃貸物件を退去する際、借主過失や通常使用を超える損耗・毀損について入居時の状態に復旧することです。
一般的な賃貸借契約では、室内のクリーニング費用など原状回復のために必要な費用は賃借人負担という特約が付けられていることが多いです。
注意が必要なのは原状回復とは必ずしも元の通りの状態戻す(傷一つなく綺麗に戻す)というわけではありません。
普通に生活していれば当然細かい傷は付きますし、小さなへこみなども生じます。
もちろん、クロスや壁に経年劣化があります。
このような故意でない傷に原状回復のための費用負担を迫ることはできません。
そのような場合の費用については原則として貸主である賃貸人側の負担となります。
その一方で、通常の使用方法の範囲を超えたり、故意や過失によって発生した損壊や汚損などの「特別損耗」については賃借人が回復のための費用負担をすべきものとされています。
建物賃貸借において一番多い苦情やトラブルの相談は退去時の原状回復費用に関するものなのです。
敷金とは不動産の賃貸契約を新規で行う際に、不動産業者を通して契約者が支払う費用のひとつです。
賃貸借契約上、債務を担保するため借主(賃借人)が貸主(賃貸人)に支払うお金のことです。
簡単に言うと契約中に大家さんが入居者から預かるお金です。
物件の退去時、借主の使用に伴い発生した修理が必要な設備がある場合、貸主は敷金からその費用を支払います。
家賃が支払えず滞納した場合にも、敷金から補填されることになっています。
敷金は保証金として扱われるお金ですので、契約期間中に家賃の滞納などが無ければ、退去時に敷金から修繕費が差し引かれた金額が返還されることになります。
これが一般的に浸透している今までの「敷金」の認識ですが、実は民法にはこういった敷金に関する明確な規定はありませんでした。
そのため、経年劣化によるもので借主に過失のない損傷の修理に敷金が使われるといった、認識の相違によるトラブルなどが発生することがありました。
原状回復をめぐるトラブルについては、当時の建設省(現在の国土交通省)が1998年3月に公表したガイドラインはありましたが、法律上は原状回復義務と敷金のそれぞれの定義や敷金の返還義務についての明記が全くありませんでした。
原状回復において起こりやすい賃貸人とのトラブルには以下の通りです。
・高額な退去時費用の請求
・経年劣化を考慮していない
・説明が曖昧
1998年に国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では原状回復に関する事は法には定められてはいませんでした。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されており、このガイドラインの内容を民法に盛り込むかたちで明文化されています。
〈原状回復の3つのルール〉
・賃借人は賃貸借が終了したときは賃借中の損傷について原状回復義務を負うこと
・通常損耗、経年変化については原状回復義務を負わないこと
・賃借人に帰責事由がない損傷については原状回復義務を負わないこと
賃借人に原状回復義務が生じる損傷は、賃借人に故意・過失、善管注意義務違反等の「賃借人に責任がある損傷」であることが明確になりました。
法改正前もこの基本ルールの中での対応がなされてきたのであり、新しいルールができたわけではありません。
改正の前後で大きく異なるのは、ガイドラインの考え方は賃借人の原状回復の一般的基準としての指針に過ぎなかったものが、法律上の基準となったことです。
第621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
出典:法務局 民法の一部を改正する法律案新旧対照条文
改正民法によって、敷金とは「借主の賃料滞納などの債務不履行があった際にその弁済に充てる」「契約終了などによる明渡しの際には、敷金から修繕費などの債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならない」ということが明確化されました。
また、賃貸借契約において、「礼金」や「保証金」といった敷金とは異なる名目で金銭が差し入れられることがあり、地域によって名目も異なることがあり、これを、改正民法ではその名目に関わらず「担保目的であれば敷金とする」と明確にしました。
その他に、敷金の返還時期を「賃貸借が終了して賃貸物の返還がされた時点で敷金返還債務が生じる」、返還の範囲を「受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額」と定めました。
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、 賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
出典:法務局 民法の一部を改正する法律案新旧対照条文
2020年4月に施行された改正民法によって原状回復義務の範囲と敷金の解釈が明確化されました。
法律で整備されたことで、敷金返還義務や原状回復に関するトラブルはきっと解消していくのではないでしょうか。
しかし、新たなトラブルを生み出す場合もありますので、十分に説明するなど細心の注意を払う必要があります。
関連記事▶︎原状回復だけで終わらせない!+αで競争を勝ち抜く方法