
賃貸管理でよくあるクレーム・トラブル6選
2020.06.25


近年、不動産業界におけるカスハラ(カスタマーハラスメント)が大きな問題として注目されています。
クレーム対応は業務の一部とされがちですが、不当な要求や暴言、長時間の拘束など、従業員の精神をすり減らすような対応を強いられるケースが後を絶ちません。
カスハラは、スタッフの離職・メンタル不調・企業イメージの悪化につながる深刻なリスクです。
この記事では、不動産業界におけるカスハラの事例と原因、企業としての対策までを詳しく解説します。

不動産業界におけるカスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客や入居者、オーナー、取引先などが従業員に対して行う、行き過ぎたクレームや不当な要求を指します。
近年は社会問題としても注目されており、厚生労働省が対策マニュアルを公表するなど、業界を超えて対応が求められています。
不動産業界は特に、入居者対応やオーナー対応、問い合わせ客対応など、関わる相手が多岐にわたるため、理不尽な要求や感情的なやり取りが日常的に発生しやすいという特徴があります。
たとえば、設備トラブルへの不満、空室が埋まらないことへの不満、接客対応への不満など、さまざまな立場からクレームが寄せられるのです。
その中には、契約内容を確認していない、あるいは説明を忘れているなど、顧客側のミスが原因であるにもかかわらず、従業員に対して大声で怒鳴ったり、人格を否定するような発言を繰り返したりするケースもあります。
電話や対面で1時間以上拘束される、同じ内容を何度も繰り返されるといった行為も深刻です。
さらに、「騒音で眠れなかったから家賃を半額にしろ」「内見が気に入らなかったから謝罪に来い」といった、法的根拠のない金銭要求や謝罪の強要も現場では実際に報告されています。
こうしたカスハラ行為は、通常業務を妨げるだけでなく、対応する従業員の精神的負担を増大させ、場合によっては人材の離職にもつながります。
不動産業界においては、顧客サービスの一環を超えた不当な対応を強いられる場面が多く存在するため、カスハラへの理解と適切な対策は、現場の安心と安全を守るうえで欠かせない経営課題となっています。
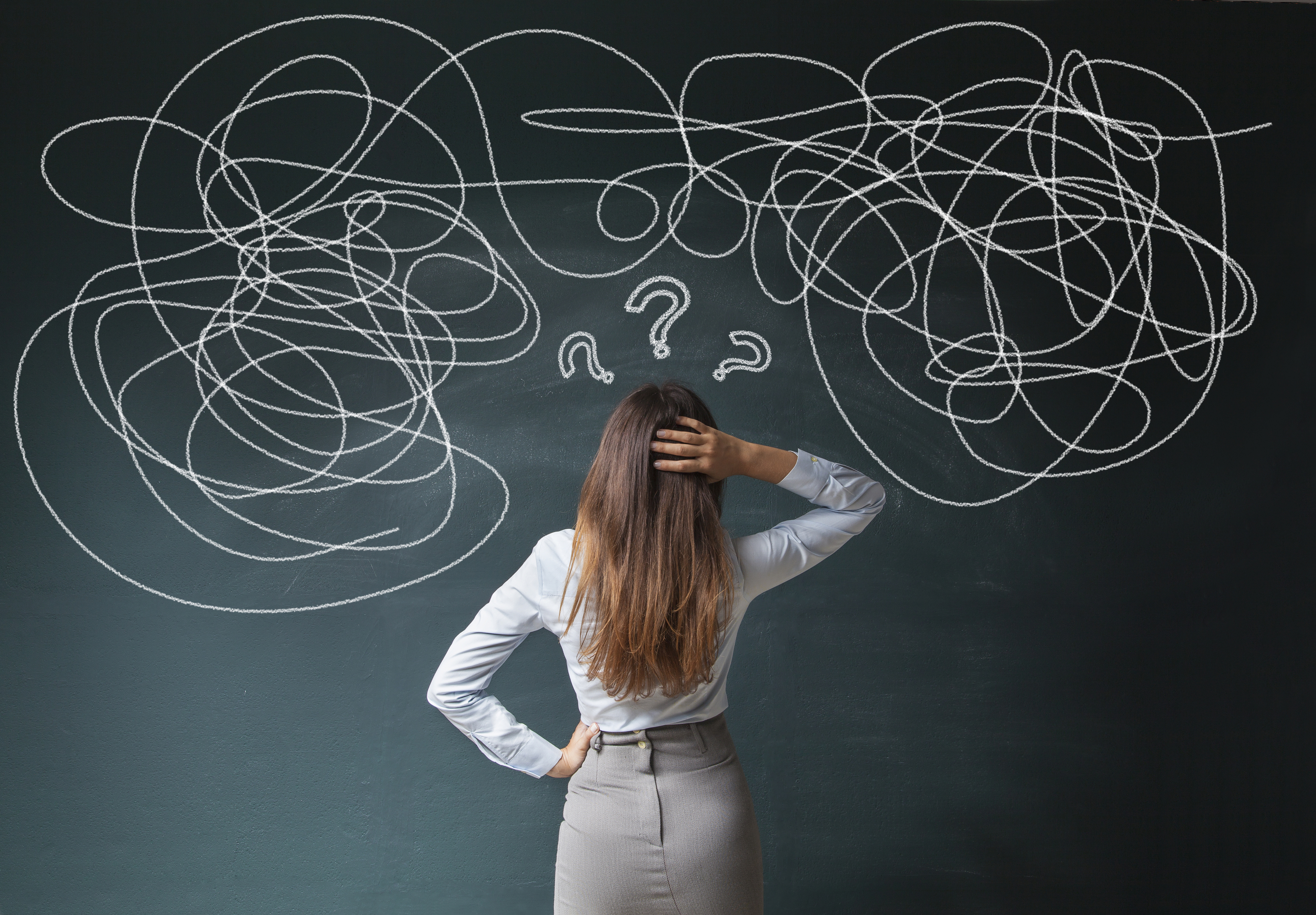
不動産業界の現場では、以下のようなカスハラが頻発しています。
不動産管理会社の現場では、入居者からの理不尽なクレーム対応が日常的に発生しています。
とくにトラブルになりやすいのが、設備不良・騒音・近隣トラブルなどに関する連絡です。
たとえば「エアコンの効きが悪い」「上の階の足音が気になる」といった問い合わせが、夜間や休日であっても頻繁に繰り返されることがあります。
営業時間外での対応が困難であることを説明しても「今すぐ来い」「管理会社なら24時間対応が当然だろう」と怒鳴り声を上げられることも少なくありません。
また、担当者が丁寧に説明し、可能な限り対応しても「納得いかない」と感情的に罵倒される場面もあります。
なかには「誰にでもできる仕事だろ」「お前じゃ話にならん、上司を出せ」と高圧的な態度を取り続ける入居者もいるのです。
深刻な事例では、「担当者を替えろ」「謝罪に来い」「土下座しろ」といった人格を否定するような要求や過剰な謝罪要求まで発展することもあります。
本来、入居者と管理会社は、契約関係に基づくパートナーですが、こうした理不尽な要求が続くと、対応するスタッフは強い心理的ストレスを抱えることになり、結果として離職やメンタル不調につながる恐れもあります。
不動産管理の現場では、物件オーナーからの一方的な要求やプレッシャーも、カスハラの一種として問題視されています。
空室や賃料下落といった収益への不満が引き金となる場合が多く、管理会社のスタッフに対して過度な圧力がかかる状況が頻発しています。
典型的なのが、「空室が続いているのはお宅の管理が悪いせいだ」といった一方的な責任転嫁です。
たとえエリアの需要や築年数、物件の設備面に課題があったとしても、それを一切考慮せず、「他社に頼んだらすぐ決まったかもしれない」「今すぐ満室にしろ」などと感情的に詰め寄られることがあります。
なかには、根拠のない損害賠償や減額要求をしてくる場合もあります。
たとえば「入居者が1か月で退去したのは、お前たちの案内が下手だったからだ」「その損失分を補填しろ」といった発言は、実際の契約内容や法的責任を超えた無理難題と言えます。
さらに深刻なのが、担当者個人に対する人格攻撃や威圧的な態度です。
「お前のせいで収益が落ちた」「そんな人間に管理を任せられない」など、業務を超えて個人の資質を否定するような発言が続くと、対応する社員の自尊心やモチベーションが大きく損なわれてしまいます。
このような状況が繰り返されることで、現場スタッフは「オーナー対応が怖い」「報告の電話をするのに勇気がいる」といった心理的負担を抱えるようになり、最終的には離職や業務品質の低下にもつながりかねません。
賃貸仲介の現場では、物件を探している問い合わせ客や内見希望者からの迷惑行為も、カスハラの一形態として問題になっています。
顧客=サービスを受ける側という立場を悪用し、スタッフに負担をかけるような行動を繰り返す例があります。
代表的なのが、無断キャンセルや直前キャンセルの常習化です。
物件の案内予約を受けて、スタッフが現地で待機していても、連絡なしで来ない、あるいは直前にやっぱり行けませんというパターンが多発しています。
一度きりであれば致し方ないとしても、同じ人物が複数回繰り返す場合もあり、対応するスタッフの時間・労力が奪われるばかりか、他の真剣な顧客対応にも影響が出かねません。
さらに悪質なケースでは、空室物件への無断立ち入りや不法侵入未遂といったトラブルも報告されています。
「鍵が開いていたから勝手に見てきた」「隣の住人にお願いして入れてもらった」など、安全面・防犯面でも非常に危険な行為が、悪気なく行われていることもあります。
実際の対応内容や事実とは異なる内容をSNSや口コミサイトに一方的に書き込む晒し行為も、企業のブランド毀損につながる深刻な問題です。
「対応が悪かった」「希望通りの物件を紹介してもらえなかった」など、主観的な不満を誇張・歪曲して投稿されることで、スタッフは精神的なダメージを受け、企業側は風評リスクにさらされます。
このような行為は、サービス利用者側にもモラルが求められるという本質を無視した、明確なハラスメント行為です。
にもかかわらず、現場では「お客様対応だから」と我慢を強いられる場面が少なくなく、企業としての対応ルールの整備と、従業員保護の仕組みづくりがますます重要になっています。
現場でよくあるのが、これは正当なクレームなのか?それともカスハラなのか?という判断の迷いです。
不動産業界では、トラブルや不満の声をすべて顧客対応として受け入れてしまいがちですが、対応の仕方を誤ると、スタッフの疲弊や企業リスクにつながります。
ここでは、カスハラとクレームの違いを明確にし、対応すべき要望と線を引くべき要求の見極め方を整理しておきましょう。
【クレームとは正当な不満や改善要求】
・契約内容と異なる対応への指摘
・説明不足・対応遅れなどに対するフィードバック
・商品やサービスの質に対する具体的な要望
これらは、企業として真摯に受け止め、サービス改善や顧客満足度向上につなげるべき重要な声です。
冷静かつ具体的であり、業務の範囲内で対応が可能です。
【カスハラとは感情的・不当・過剰な言動や要求】
・暴言・人格否定・大声での威嚇
・法的根拠のない金銭要求(例:慰謝料を払え)
・過剰な謝罪要求(土下座・訪問強要)
・長時間の拘束や執拗な連絡
・SNSでの名指し中傷や“晒し行為”
こうした行為は、サービス改善や顧客満足とは無関係なハラスメント行為です。
企業としても、毅然とした対応と記録保全が求められます。
すべてに応えること=良い会社ではなく、線を引くこと=社員を守る企業姿勢であるという価値観を社内に浸透させることが、不動産業界における持続可能な顧客対応の第一歩です。

不動産業界におけるカスハラの問題は、個々の担当者の努力だけでは解決できません。
企業としての明確なスタンスと仕組みづくりが不可欠です。
以下では、不動産会社が実践すべきカスハラ対策を5つの観点からご紹介します。
1.カスハラ対応マニュアルの整備と社内共有
まず取り組むべきは、クレームとカスハラの境界線を明確にしたマニュアルの作成と周知です。
どこまでが「対応すべき苦情」で、どこからが「対応不要のハラスメント」なのかを明文化することで、スタッフの迷いや不安を軽減できます。
【マニュアルの記載内容の例】
・クレーム対応の基本方針と姿勢
・ハラスメントと判断する基準
・暴言・長時間拘束・金銭要求などへの対応例
・エスカレーションフロー(上司・法務部・顧問弁護士など)
定期的な研修やロールプレイで実践的に学べる機会を設けると、現場対応力の底上げにもつながります。
2.記録・録音の徹底とシステム整備
万が一トラブルに発展した場合に備え、対応履歴の記録・保存は必須です。
・電話対応はすべて録音
・クレーム内容は日時・内容・担当者名を日報や顧客管理システムに記録
・対面時も、事前に「録音・記録を行います」と掲示し抑止力にする
記録が残っていれば、スタッフの正当性を証明する資料となり、万が一訴訟や行政対応が必要になった場合にも有効です。
3.担当者を一人にさせないチーム対応の徹底
カスハラが深刻化する背景には、スタッフが孤立して対応を抱え込んでしまう構造があります。
特に若手や経験の浅い社員は、理不尽な言動に直面しても「我慢しなければいけない」と思い込みやすく、精神的に追い詰められてしまいます。
そこで重要なのが、複数人での対応・上司の即時介入体制です。
・苦情の受付時点で上長に情報共有
・初期対応以外は、2名以上でフォロー
・エスカレーションをためらわない文化を醸成
ひとりにさせない仕組みを作ることが、従業員の安心と企業としての継続対応力につながります。
4.外部リソースとの連携(法務・弁護士・相談窓口)
悪質なカスハラは、企業内部だけでの対応が困難な場合もあります。
そのため、法的視点からの助言や対応ができる体制をあらかじめ整備しておくことが重要です。
・顧問弁護士との連携ルートの明確化
・必要に応じて内容証明郵便などの法的対応
・厚労省や自治体が提供する外部相談窓口や対策セミナーへの参加
顧客と争いたくないからとすべてを受け入れてしまうのではなく、毅然とした対応で企業と社員を守る姿勢が求められます。
5.スタッフのメンタルケアと職場環境改善
カスハラ被害は、精神的なダメージとして蓄積し、職場不信や離職リスクを高めます。
企業としては、心のケアまで含めた対応体制の構築が必要です。
・月次面談や定期アンケートで心理状態をチェック
・社外カウンセラーの紹介制度
・スタッフの声を吸い上げるボトムアップの仕組み
「つらいと思ったら相談できる」「無理に我慢しなくていい」という心理的安全性を職場に根づかせることで、長期的な人材定着と組織力の強化につながります。
不動産会社にとって、顧客満足の追求は重要です。
しかしそれは、「すべての要求に応える」こととイコールではありません。
従業員が安心して働ける環境があってこそ、質の高いサービス提供が実現するのです。
カスハラへの対策は、企業文化・リスク管理・人材定着のすべてに関わる重要テーマです。
個人任せにしない、組織として守る体制づくりを今こそ進めましょう。
-----------------------------------------------------------
不動産テックのTATSUJIN JOURNALでは、最新の不動産トレンド、不動産テック、賃貸仲介・売買の業務改善事例、セミナー情報などお役に立つ情報を日々発信しています!
日々変わりゆく、時代の変化に応じた取組みが今まで以上に必要となってきました。
そこで、賃貸管理会社の皆様のお悩み、課題を解決するために、不動産に関する最新の情報をご提供しております。
その他、賃貸管理会社の皆様にお役に立てる情報をメルマガ・LINEにて配信しております。
こちらもぜひご登録お願いいたします!
-----------------------------------------------------------